
【醸造家が語る定番ビールの魅力】「COEDO 毬花-Marihana-の魅力やこだわり」
醸造家の尾崎さん COEDO 毬花-Marihana-とは 毬花-Marihana-は名前にもある通り、ホップをふんだんに使用したビールになっています。(毬花はホップの花を意味しています。)特に...

醸造家の尾崎さん COEDO 毬花-Marihana-とは 毬花-Marihana-は名前にもある通り、ホップをふんだんに使用したビールになっています。(毬花はホップの花を意味しています。)特に...

埼玉観光物産協会が運営する、埼玉県の魅力を発信するサイト「ちょこたび埼玉」主催の日帰りバスツアーが開催されます! 訪れるスポットは、「COEDOクラフトビール醸造所」と「武蔵ワイナリー」2か所...

あんぱんの元祖木村屋總本店さんと、ライフスタンス・アソシエーション「PARaDE」で繋がり、「発酵から始まる新たな価値創造」をテーマにコラボレーションプロジェクトをスタートさせて頂く事になりま...

1932年創業以来、手仕事によるガラス製造にこだわり、ガラスの特性を熟知した職人自らが、開発者であり、デザイナーとして日々ガラス製造に情熱を注いでいる”Sghrスガハラ”。これまでCOEDO定番...
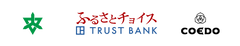
埼玉県東松山市、コエドブルワリーとふるさとチョイス、COEDOクラフトビール醸造所が舞台のキャンプ型音楽フェスチケットをふるさと納税のお礼の品として受付開始<4月15日より>~「...

5/27(⼟)・5/28(⽇) の2⽇間埼⽟県東松⼭市COEDOクラフトビール醸造所敷地内で開催キャンプ型⾳楽フェス「⻨ノ秋⾳楽祭(むぎのときおんがくさい)」クラウドファンディングをスタート!黄...

醸造ポリシーへの共感と敬意、そして双方の技術的な発展を目指して、台湾のクラフトブルワリー<SUNMAI>とのコラボレーション醸造を、2019年以降毎年行っています。 2019年にCOEDOブル...

ビールは、とっておきの料理との相性を楽しんだり、仲間とともにグラスをひたすらあけまくったり、或いはハレの席での乾杯であったり、料理を作りながらの一杯であったり、様々な形で私達の日常生活に溶け...